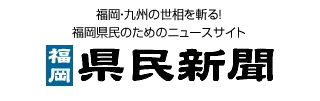(08年4月号掲載) 本紙はこの事件について、共犯者(有罪が確定)の供述を捜査当局が"捏造"し、藤原さんを「黒幕」に仕立て上げた可能性を指摘していた。鈴木裁判官は有罪の判断を下したわけだが、その判決理由には理解し難い点が多く、まさに「まず有罪ありき」。かねてから捜査当局偏重と指摘されてきた日本の刑事裁判の、典型例と言える。 検察側の言い分をほぼ認め、藤原さん側の主張はまったく無視した形となった鈴木裁判官の判決。その内容を検証してみたい。 「被告を懲役2年に処する」。着席するよう促されてもそれを拒んだ藤原さんは、判決文を読み上げる鈴木裁判官を直立不動のまま見つめ続けた。「ひどい判決です。裁判所を信じていた私がバカでした」 判決によると、藤原さんは06年、ほかの2人と共謀し、セクハラ行為を理由に教育長を脅し金を奪おうと計画。8月末から9月にかけて現金6000万円を要求したが失敗した。 裁判の大きな争点の1つとなったのは共犯者A氏の供述だった。 藤原さんは、A氏からセクハラ行為の話を聞き「不倫通告書」と題した文書を作成、これを教育長宅に送るなどした。その理由について「女性を職場から辞めさせようとしていると聞いたので、それを止めたかったから」と主張していた。 A氏は当初、警察の調べに対して「要求する金額や分け前について藤原さんと事前に話し合った」と供述したが、公判に入ると「警察から『共犯者がいた方が罪が軽くなる』と無理やり誘導され、嘘の供述をしてしまった。藤原さんは恐喝には無関係」と一転させた。 だが鈴木裁判官は「警察の捜査段階での供述は具体的かつ迫真性に富み、矛盾がなく自然(注:こうしたケースでの常套句である)」などとして「信用できる」と結論付けた。 仮に警察による誘導・捏造があったのなら、その「作られたシナリオ」が具体的で矛盾がないのはごく当然である。また、警察での供述が事実ならば、何の得にもならないのになぜA氏は公判で嘘をついたのか。判決はその理由について一切触れていない。 一方、鈴木裁判官が「公判での供述は信用できない」とした最大の理由は「信用すべき捜査段階での供述と反するから」 このような論理を展開する裁判官にかかると、いったん捜査段階でした供述を公判で翻そうと思っても、事実上不可能なのである。 藤原さんは「06年8月9日、初めて県教育庁を訪れセクハラ行為に関する文書を渡した。調査をしてもらうためだった。恐喝しようとする者が事前に情報を第三者に漏らして公にするはずがない」と主張していた。 今年1月17日、検察側の証人として出廷した県教育庁のN氏、S氏はそろって「初めて藤原さんが訪ねて来たのは(恐喝が失敗した後の)9月4日」と述べ「9/4藤原さん、突然来室」などと書かれた1枚のメモ用紙のコピー(原本ではなく)を証拠提出した(2人の証言とメモについては、きわめて不自然であることを本紙HPで指摘した)。 鈴木裁判官は「公務員である2人の証言は信用できる」とする一方、「8月21日 教育庁」(注:藤原さんは2回目の訪問と主張)と書かれた藤原さんのメモ帳の存在にはまったく触れなかった。 藤原さんは逮捕直後から「マスコミや県に聞いてくれ」と話していた。だから、本来であればもっと早く提出されて当然の証拠がなぜか再開後の、それも論告求刑直前になって出された。そしてこれが、藤原さんの主張を否定する決定打となった。 この裁判は、A氏が供述を一転させて以降、公判検事がころころ代わり昨年9月、わずか半年あまりで結審。だが鈴木裁判官の判断で再開し、情報提供の時期をめぐりあらためて審理するという、異例の事態となった。その過程と新証拠の提出時期、そして判決内容を総合すると「なぜ裁判官は審理を再開したのか」という理由が透けて見える。 一言で言えば鈴木氏は、「捜査当局寄り」と指摘される日本の裁判官の、まさに典型である。これまで無罪判決はほとんど出したことがなく「彼は捜査当局大好き裁判官として有名ですから。運が悪かったですね」(ある司法担当記者)。「警察の捜査はいつも適正」「公務員は嘘をつかない」。今時、実に"希少"な考え方が裁判所を支配している現実を示す好例と言える。 「有罪率99.9%」。日本の警察・検察の「優秀性」を示すものといわれてきた数字。だが、この高い値を支えているのは鈴木氏のような裁判官でもあることを、再認識すべきだろう。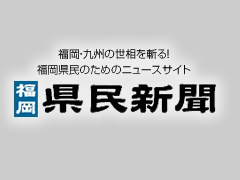
 二丈町教育長への恐喝未遂事件の裁判で、無罪を主張していた藤原正男被告に対し福岡地裁(鈴木浩美裁判官)はこのほど、懲役2年(執行猶予4年)の有罪判決を言い渡した(HP既報)。
二丈町教育長への恐喝未遂事件の裁判で、無罪を主張していた藤原正男被告に対し福岡地裁(鈴木浩美裁判官)はこのほど、懲役2年(執行猶予4年)の有罪判決を言い渡した(HP既報)。
理解し難い判決理由 捜査当局偏重「刑事裁判の現実」 [2008年5月13日12:00更新]
タグで検索→ |
捜査段階の供述は「絶対」
公務員は嘘つかない
運が悪かった・・?