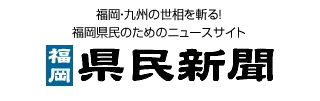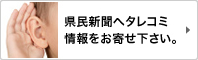今年2月、岐阜県の高校1年生(16歳)と東京都と滋賀県の中学3年生(15歳と14歳)の3人を不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺で警視庁が逮捕した。
昭和生まれの世代には中々理解できない事件だが、そもそも遠く離れた3人が、どうやって知り合い、いつから犯罪に走り、多額の金銭をどうしていたか、分からないだろう。
先ずもってITに詳しい関係者は、この3人が映画に出て来るような凄腕のハッカーではないことを断言している。
誰でも入手可能なプログラムや対話型生成AI(人工知能)と、一般的なハッカーの間で使い回されているツールを使えばできる犯罪、もっと言えば狙われた楽天モバイルのセキュリティの低さを指摘している。
この3人、元々はオンラインゲーム等で知り合い、チャットで親交を深め、中高生だけに面白半分で「金が欲しい」や「ハッキング技術」の話がきっかけで、暴走が始まったのではなかろうか。
彼らは個人のIDとパスワード33億アカウント分を仮想通貨で購入、そしてセキュリティも緩い上に、追加で本人確認書類無しで15個の携帯番号を取得できる楽天モバイルに着目した。
これで70件近いアカウントの不正アクセスに成功、約2500件の携帯番号を手に入れ、テレグラムを使い1件3000円ほどで販売、中高生では考えられない約750万円の仮想通貨を手に入れていた。
事件で使われたチャットGPTは不正プログラムなどの作成を実行しない設定になっている模様であるが、これもネット上には特殊な指示を出してAIを騙し、悪意のある指示に従わせる手法が開示されており高い技術や知識は必要ない。
小中高生のITリテラシーを止める必要はないが、モラルや犯罪意識の教育を徹底しなければ、今後はとんでも無い日本になるような気がしてならない。

こんな記事も読まれています