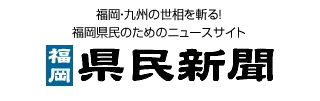右官と左官
今回登場願うのは、大分市在住で「鏝絵(こてえ)の仁五」を名乗り、滅び行く左官の匠の技を後世に伝えるべく、努力している後藤仁五氏である。
左官の語源は一説によれば、今から1300年前の奈良時代にまでさかのぼる。当時の建物は柱などの構造物を大工が立て、壁や瓦などは漆喰職人が作業、この2つの職種で建物は建築されていた。内裏や公家の住居、寺院の伽藍など、建築物はすべて朝廷の意向で建てられるが、官位が無ければ朝堂などに上殿することが出来ない。そこで大工を右官とし、漆喰職人に左官という官位を与えたもので、大工の右官は棟梁に変わったが、左官はそのまま職種として残ったものと言われている。
後藤仁五氏は商家の生まれで、学業を身に付けたかったのだが、家庭が複雑で家にいたたまれなくなって、中学を卒業すると同時に家を出た。当然「手に職を」と考え、左官職の親方の下へ弟子入りした。前述したように昔の家は左官職人の仕事が大半で、特に代名詞ともいえる壁は竹組の上に3層の工程が必要とされる。まず赤土だけの粗塗、次に赤土と砂、切り藁を混ぜて中塗して、最後に白い漆喰で整える。そして台所のかまどや流し台も、こて1つで器用に作成、そして土間や玄関のたたきなども左官職の工事範囲内だった。
しかし弟子入りした当初から、こてを握れるはずもなく、最初は漆喰の下地として使う赤土を練り上げる力仕事の連続で、途中で逃げ出す人も少なくなかった。一通りの修業を積み、一人前のこて使いが出来るようになり、若くして24歳のときに独立し、左官職人として請負業の道に入った。
左官職が要らなくなった
独立してから20年近くは真面目な仕事振りと確かな技術力を評価され受注も多く、利益も出し潤っていたが、余裕が出来て趣味で始めたモーターグライダーの墜落事故で事態は一変した。片足を切断しかねないほどの大事故で、生死の境をさまよったほどだったという。
悪いことは重なるもので、建築工法が大きく変化していく時代の波にも直面した。壁は赤土を何層にも塗り、さらに白い漆喰で上塗りするため、乾燥には時間が必要で、住宅建築が長期間にわたる要因でもあった。しかし左官職の代名詞でもあった漆喰の壁は軽量の不燃ボードに代わり、風呂や洗面所はタイル貼りからユニットバスへ、また台所はシステムキッチンに取って代わられ、工場生産で多くの製品が市場に出回ると、左官職が腕を振るえる仕事はあっという間に無くなってしまった。
経営していた会社も、社長が不在の中では業績が急降下し倒産するのは当然で、先祖から引き継いできた財産もほとんど失うことになった。
鏝絵の制作へ
生死の瀬戸際から生還したものの、左官の仕事が無くなった仁五氏が、会社を整理した後に、これからどうしようかと考え、新しく居場所を見つけ出したのは鏝絵の世界だった。
大分地方、特に豊後から日田、さらに筑前朝倉地方にかけては、古くから土蔵や店舗などの壁面に、左官職人が自らの仕事の証を示す意味で残していた、鏝絵に目が向いた。豊後の鏝絵師「鏝絵の仁五」の誕生である。
もともと鏝絵は、こて1つで漆喰を立体的に盛り上げ、七福神などの福を招く象徴や、花鳥風月、また火災防止を祈願するために水神の龍などを題材としている。江戸中期に静岡県出身の名工入江長八が、芸術の域にまで昇華させた開祖と言われている。大分へもその弟子が伝えたものだが、現存している鏝絵は大部分が左官職の手すさび程度の職人技のレベルでしかなかった。
新たに鏝絵の制作を始めた仁五氏の初期の作品は、墜落事故の影響で神仏に対する謝恩の気持ちが強く、扱う題材にも偏りがあったが、次第に心も落ちつきを取り戻し、幅広いテーマに挑戦するようになったようだ。
仁五氏が目指したのは単に漆喰を山形に盛り上げるレリーフではなく、足や腕や頭が壁面から飛び出し、浮き上がり、奥行きがある立体感を持った漆喰彫刻ともいえる作品だ。だから材料の漆喰も粘着性を強く持たせる工夫を施し、使用するこても工程ごとに変えた。特に仕上げには細かい部分が増えるため、1つの作品を制作するためにへらの大きさや角度が異なる、100種類以上のこてを自ら加工したこともあるという。
鏝絵の新しい領域
これまでは、外壁を飾ることが主流だった鏝絵だが、最近は内装業界でも注目され始めてきた。上の写真は、昨年10月に名古屋駅前の地下街天井に飾られた3点の鏝絵の1つ、雷神の像。地下街通路の角々の天井に飾られているもので、風神、雷神、そして龍神の組み合わせ。それぞれ縦2メートル×横1.5メートル、奥行きが50センチメートルあり、見事なレリーフである。白一色で作られているのだが、光を当てることで陰影が生じ、立体感がより強まるだけでなく、光の色を変えることで、受け取るイメージが大きく変化し、評価が高まっているという。
下の写真は中洲ゲイツビルの焼肉レストラン「肉匠利休」の入口を飾っていた1.5メートル四方のレリーフ。元オーナーの梨田現WBCヘッドコーチがモチーフだった。

 また下の写真は、昨年7月に名古屋の大和屋守口漬物総本舗が、東京大丸食品街ほっぺタウンに出店した際、商品である「魚介味醂粕漬鈴波」の看板として店に飾られたもの。縦70センチメートル×横2.5メートルの長方形だが、モニュメントとしても充分に存在価値をアピールしている作品。
また下の写真は、昨年7月に名古屋の大和屋守口漬物総本舗が、東京大丸食品街ほっぺタウンに出店した際、商品である「魚介味醂粕漬鈴波」の看板として店に飾られたもの。縦70センチメートル×横2.5メートルの長方形だが、モニュメントとしても充分に存在価値をアピールしている作品。

今年も新たな鏝絵制作で忙しい。大和屋守口漬物総本舗から引き続き、2月一杯が納期の2つの作品を受注しているからだ。松坂屋デパート名古屋本店地下街の店舗に飾られるもので、1つは商品名「鈴波」の看板で、縦1メートル×横4.2メートル×奥行き15センチメートル。もう1つは、鮭が樽から飛び出すさまを表したモニュメントで、ショーケースの中に置かれるが、大きさは縦1メートル×横1.2メートル×高さ25センチメートルと大きい。
今年65歳を迎える仁五氏は、工房での制作が日課で、数年前からは三男も仕事を手伝い始めており、後継者として育成を進める一方、自らは職人技を芸術の域に引き上げるべく力を注いでいる。
夢は先人から受け継いできた伝統文化としての鏝絵を、現代の建物に融合させることが出来る、古いながらも新しい技術や領域を切り拓き、さらに極めることが出来ればというもので、まだまだ意欲は旺盛だ。

こんな記事も読まれています
建築工法の変化で、左官の仕事が激減し倒産 鏝絵(こてえ)を職人技から芸術作品へ昇華 豊後の鏝絵師 後藤仁五さん(65歳) [2013年2月19日16:45更新]
タグで検索→ |